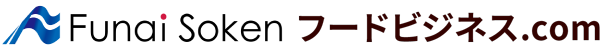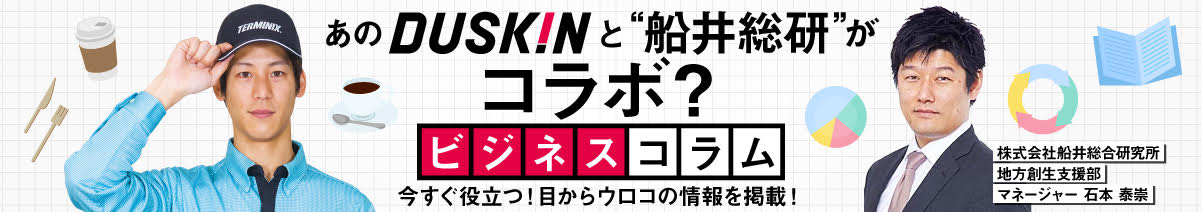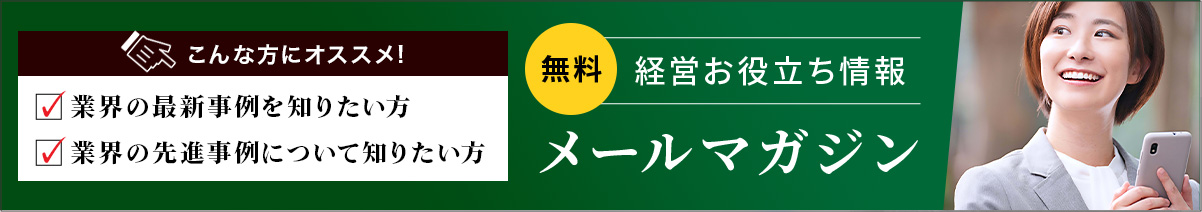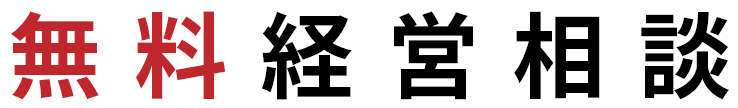国内最大級の経営コンサルティング会社の「フードビジネス専門サイト」

外食・中食ビジネス
評価制度構築コンサルティング
関連コラム
後継者育成プログラムはどのようにすればいいのか?飲食店経営における事業承継の方法【解説】
いかにして次代へ経営を存続させていくのか?経営者の高齢化が進む中で、昨今、飲食店経営の現場においても非常に重要なテーマになってきています。事業を次代に引き継ぐ方法としては、後継者が不在の場合は、M&Aによる事業譲渡ということもありますし、株式上場などによる「資本と経営を分離する方法」もあります。
しかしながら、私たちがご支援させていただく飲食店を経営する多くの中小企業の場合、子供への事業承継の形態が最も多いです。
(子供へ引き継ぐ前に別のファミリー等が引き継ぐ場合もあります)
実際、当社の多くの中小企業のクライアントは創業者よりも後継者のほうが圧倒的に多く、
また、創業者をご支援している場合でも、ご支援が長く続いているうちに、後継者の育成がテーマとして上がってきます。
「事業の継続」「会社の永続」ということを目的とした場合、後継者育成は多くの中小企業にとって重要な経営課題でもありますので、様々な研修や支援サービスが存在します。
取引先金融機関や商工会議所などからも各種サービスを紹介されることもあろうかと思います。
私たちの経営コンサルティングというサービス提供においても、
「会社の将来を担う経営者の育成(=後継者育成)」は10年スパンで見たときには必須の支援テーマに上がってきます。
では、どのような方法で後継者を育成していけばいいのか?どのような内容のプログラムを策定するのが後継者の成長につながるのでしょうか?またどのようなマネジメント体制をとっていけばいいのでしょうか?
ここでは、私たちのご支援先で進めている実際の後継推進の事例に基づいて後継者育成プログラムについて解説致します。
現場を知る機会を作る
企業規模の大小を問わず、従業員にとっての会社全体のリーダーは現社長です。若くして創業した創業者が長く経営を担ってきている場合、「30年程度リーダーは常に現社長である」というケースも多々あります。それを引き継いでいく後継者は一般的には幹部社員よりも若いですから、通常は「次の社長はリーダーとして優秀なのか?!」といった目で品定めされるものです。
このような事業承継においては
「新社長はキチンとわれわれの現場のことを知っている」「飲食業界特有の仕事内容について理解している」
という認知を形成することがまず大切になります。いくら頭が良くて優秀な大学を卒業していても、「飲食店の現場のことは全くわかってない・・・」と思われてしまうと、リーダーシップを発揮しずらくなってしまいます。
マクドナルドではどのような上級職のキャリア人材であったとしても必ず現場体験をすることになっているようですが、「現場のこともわかったうえでの経営執行」であると認識してもらうことは大切なことです。
また、自社の現場のみならず「他社の現場を知っている」ということもリスペクトの要素になります。「〇〇チェーンの現場ではこのような仕組みで運営されているから、このような結果につながっている」など他社の現場体験は「現場のことをよく知っている」という印象に繋がっていきます。
可能であれば自社へ入社する前に、
「外食チェーンでのアルバイト経験を複数社積んでおく」
「他社へ就職し他人の釜の飯を食う」
などの経験値を持っておくことは非常に大切なことです。
他社の成功事例や失敗事例を学ぶ
また、社内でリーダーシップを発揮していく場合、自社内の目線のみならず、外部環境がどのように動いているのか?を知っておくことは非常に大切なことです。経営を上手にするコツは「時流適応」です。世の中の流れを知ることは、自社の長所を正しく把握し、その強みを磨き伸ばすことと同じくらいに大切なことです。
他社はどんなことをして成功しているのか?また失敗しているのか?
特に飲食店ビジネスにおいては、新業態の登場が次々に起こる市場ですので、社外の新しい取り組みに目を向けることは大切です。
具体的には、繁盛店の視察を定期的に行うことが重要です。月に5軒は少なくとも他社の飲食店を見に行くのが良いと思います。自社の店舗があるエリア外(他県のみならず海外も)へ視察に出かけることが大切です。
視察店舗や視察先企業では、その店舗の「長所探し」をするのがポイントです。また、人は忘れる生き物なので、視察後にはメモを残す習慣をつけるのが良いです。
そして、本を読むことも大切です。
業界誌のみならず、経営でベストセラーになっている本を読むことは非常に重要です。読んだ本で学びになったポイントを箇条書きにし、さらに「自社に活用するならばどういうやり方をすればいいのか?」を考えて、言語化するプロセスを踏み続けることが経営者としての当事者意識の向上にも繋がり、経営者としての血肉になっていきます。
また、セミナーや経営者が集う勉強会にも参加し、他社の取組み(成功・失敗両方)を聞くことが大切です。先輩経営者から「こんなことをやっておいたほうが良いよ」や「こんなことをやって自分は失敗したから、注意したほうが良いよ」などのアドバイスは参考になるはずです。当社の創業者の舩井幸雄さんは「経営者の“師と友づくり”をお手伝いしなさい」と仰っておられました。私たちが運営する経営研究会はそのような場として私たち自身も大切に継続運営しております。
「自社の外側」にある情報を積極的に取り入れることがポイントです。
自社内でのプロジェクト推進
上記のステップで経営者としての力をつけながら自社の業績向上を実現していくための仮説を立てて(分析⇒計画立案)、「実践」することが大切です。実践することで成功も失敗も経験することになりますが、「実体験」が最も経営者を成長させてくれます。特に社内でのプロジェクトとなると、失敗も成功もそのリーダーシップを発揮した後継者の能力として従業員から評価されます。
「失敗は成功の母」ですし、100戦100勝とはなりませんが、
「確実に前進していること」、
「前よりも良くなりつつある」、
「失敗したものの積極的なチャレンジであったこと」
などプラス要素はあるほうが良いと言えます。
さらに、そのプロジェクトを従業員を巻き込みながら実施し、社員・スタッフの参画意識を高めながら、一緒に成功に導いていくことができると、従業員にとっても「自分を成長させてくれる新しいリーダー」として「一体感」も育まれます。
そして、従業員参画型プロジェクトを進める上では、「対話型・双方向のコミュニケーション」が大切になってきます。プロジェクトに関わるメンバーとのコミュニケーションの質を高めるために時には社外に出て「合宿」など非日常シーンを創出することも効果的です。一緒に社外の事例を学びに出かけ、繁盛店の現場を体験し、自社に良いところをいかにして取り入れるのか?議論しあい、目線を合わせることを経ることで組織の一体感が増します。
具体的な社内プロジェクトとしては、
「デジタルトランスフォーメーションの推進」(現場、本社、マーケティング活動など)は若いリーダーほどデジタルに親和性が高く、また生産性向上の観点からも経営の重要テーマですので、オススメです。
また、中小企業の場合は特に、
働き方改革の推進、労務環境の整備、それらを具現化するための「人財開発(採用・定着化・戦力化・評価制度作りなど)」をテーマに関連したプロジェクトの推進も重要です。
時代の要請も日に日に高まっておりますし、少子高齢化が進む日本市場においてこれら人事、マネジメント系のテーマは経営上も優先順位が非常に高いです。
そして、「新規事業開発」関連のテーマも重要です。
コロナによって従来のビジネス構造からの脱却がいま外食業界においては多くの会社にとって必要になっていますので、事業構造の転換は喫緊の経営課題です。
既存店舗のリニューアルや業態転換による新規事業開発、新立地(いままでビジネス展開していない領域)におけるビジネスモデル開発など、ウイズコロナ~アフターコロナに向けて会社の成長をけん引する事業の開発は非常に重要なプロジェクトです。
このような社内プロジェクトにおいてリーダーシップを発揮し、会社を前進させ、従業員を巻き込みながら参画型経営を推進することで新しいリーダーとしての経験値を高めることが、後継者を成長させる機会に繋がっていきます。
ビジョン発表の機会を作る
これらの動きを踏みながら、節目となる代替わり(世代交代)のタイミングにおいては、新リーダーが新しい未来を従業員に自分の言葉で伝える場(=ビジョン発表会、経営方針発表会、中期経営計画発表会など)を設けることが大切です。
このような場においては新リーダーに対する従業員の不安を払しょくし、「よし!この若い新しいリーダーについていこう!」と思ってもらうことが大切です。
さらに、幹部社員を巻き込みながら、幹部社員にも担当事業や担当セクションの計画策定&ビジョン発表を担わせることによって、当事者意識、参画感を高めることが大切です。
後継者のみならず、次世代のリーダーシップを一緒に担っていく幹部人材も
このような場に立つことで「リーダーとしての責任感」が高まります。
良い緊張感を持ち、しかしながら「明るい未来を創っていくことに挑戦・コミットする当事者意識」をリーダーとして、新しい経営チームとして持つことが後継者をさらに成長させるキッカケになっていきます。
ぜひ、このような節目の場を作りましょう。
あとは、失敗を恐れず積極的に前向きなチャレンジをすることが大切です。
皆様の会社におかれましても次代を担う後継者育成を進めるにあたって、上記の流れを参考にしていただければと思います。
▼外食業界時流予測レポート2022を無料ダウンロード!▼
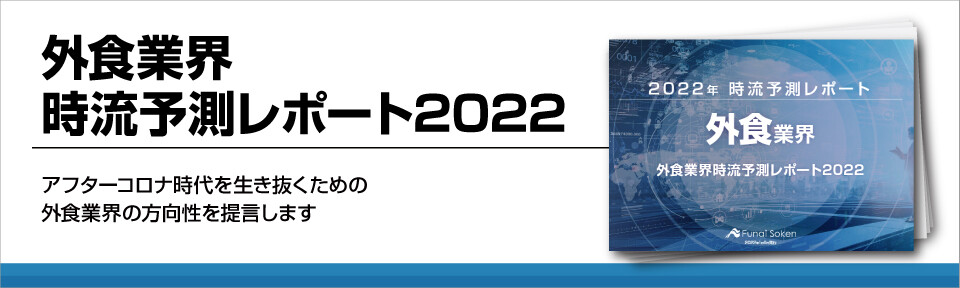
タグ一覧
- ★人手不足(92)
- ★収益性(103)
- ★新規事業(84)
- ★生産性(92)
- HACCP(1)
- web(88)
- インバウンド(8)
- カフェ(50)
- コスト削減(84)
- スマホ対応(4)
- テイクアウト(12)
- ビジネスモデル(5)
- ブランディング(11)
- ロボット(2)
- 中華・ラーメン(41)
- 事業承継(1)
- 人手不足(2)
- 人材(2)
- 人材採用・教育(6)
- 人材教育・評価制度(53)
- 働き方改革(25)
- 出店(57)
- 出店・リニューアル(107)
- 利益・収益UP(113)
- 和食店(3)
- 宅配・デリバリー(232)
- 寿司・海鮮(52)
- 居酒屋(73)
- 店舗内装工事(1)
- 後継者育成(1)
- 必要資金と資金調達(1)
- 採用(57)
- 新型コロナ対応(18)
- 新業態(107)
- 新規開業・開店(6)
- 業態別飲食店の開業から販促までのポイント(5)
- 業績改善・売上UP(5)
- 焼肉(83)
- 物流(1)
- 物流・配送(9)
- 生産性(1)
- 畜産(1)
- 目標(9)
- 看板・デザイン(1)
- 石本 泰崇(1)
- 立地・物件探し(1)
- 給食(15)
- 菓子・パン(16)
- 衛生(1)
- 補助金(3)
- 観光(8)
- 計画・目標(35)
- 農業(7)
- 配送(3)
- 集客(1)
- 集客(109)
- 顧客管理(18)
- 食品(4)
- 食品メーカー・卸(15)
- 食品小売り(17)
- 飲食店(31)
- 飲食店の事業計画書(1)
- 飲食店の運営ノウハウ集(9)
- 飲食店開業のノウハウ集(3)